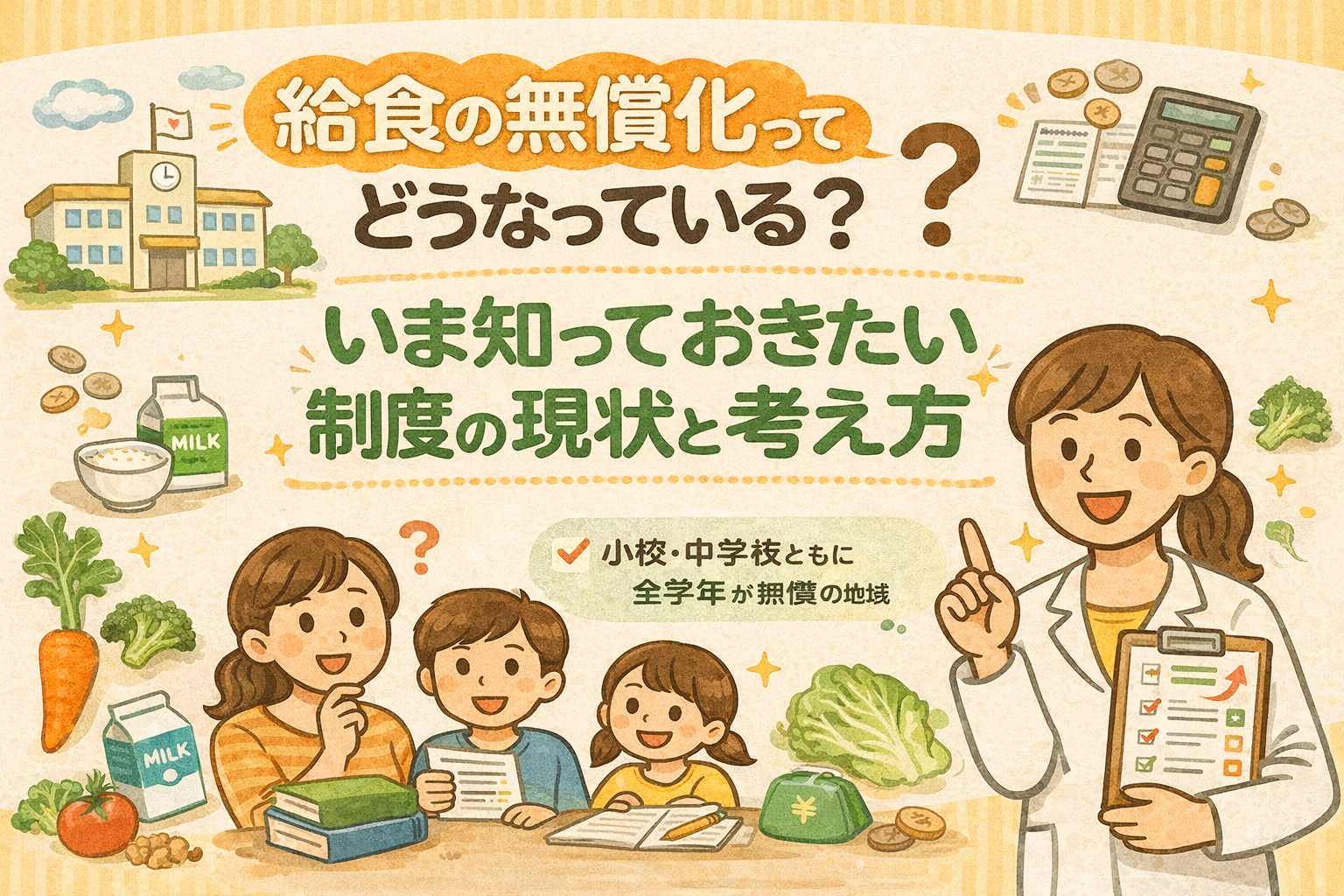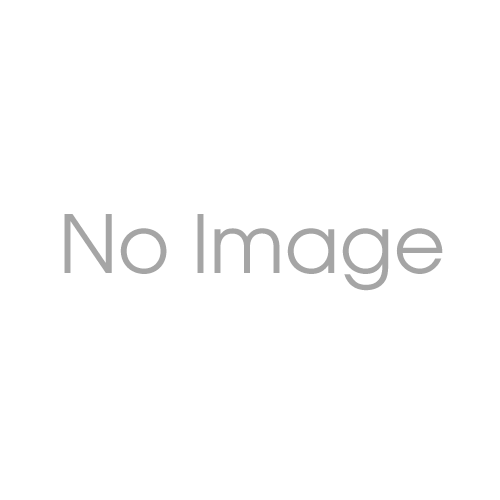
食と栄養のスペシャリスト「栄養士」と「管理栄養士」は、業務内容がそれぞれ異なります。今回は、栄養士と管理栄養士の資格の違いや活躍場所、キャリアパスについて解説します。一度現場を離れて仕事復帰を考えている方は、この記事を参考に活躍する場の選択肢を広げてみましょう。
栄養士の資格取得のための条件
栄養士の資格は、厚生労働大臣が指定した栄養士養成施設もしくは管理栄養士養成施設で必要な課程を履修して卒業し、栄養士免許申請をすることで得られます。養成施設には専門学校や短期大学、4年制大学などがあり、基本的にはどの施設を卒業しても同じ「栄養士」の資格が得られます。
授業やカリキュラムは各施設により違いがあり、各専門分野の知識・技術をより深く学ぶ施設や、実践的技術を身に付け人材を育成する施設、ほかの資格も取得できる施設などさまざまです。
管理栄養士の国家試験とは?
管理栄養士の資格は、食に関して障害がある方、療養中の方、高齢者など、特別な配慮が必要な方それぞれに栄養指導も行える、栄養士の上位資格です。栄養士の持つ知識に加えてより高度な専門知識が必要なため、国家試験を受けないと取得できません。
国家試験を受けるには、管理栄養士養成施設(4年制)を卒業するか、栄養士養成施設での年数と実務経験が合計5年以上であることが必要です。なお、試験はマークシート形式で、午前・午後に分け約5時間行われます。
栄養士の主な仕事内容
栄養士の仕事は、個人または集団に対し健康な食生活を送れるよう、栄養学の知識に基づいたアドバイスやサポートを行うことです。栄養バランスの取れたメニュー考案や、調理方法の改善、食や健康に関する正しい知識・技術の伝達を行います。
管理栄養士の役割と責任
管理栄養士は、健康に配慮が必要な方に対しても栄養指導を実施します。学校や病院、福祉施設、保育園、給食会社、食品会社などが活躍の場となります。大規模給食施設では、管理栄養士が施設の管理や労務管理も行うことが多いのが特徴です。
管理栄養士は、厚生労働大臣の定める基準を満たす施設には、必ず配置しなければならないとされています。栄養士より高度な専門知識を持っている、国に認められた存在として、知識と技術を活用することが求められているのです。
学校や病院での栄養管理業務
学校では、成長期に必要な食事と栄養の知識を提供します。主な実務は、献立作成・食材発注・給食調理などです。供給した給食・献立を振り返り、次の献立作成や調理に活かします。子どもたちへの食育や、食生活の改善、食物アレルギーなどへの個別指導も業務に含まれます。
病院では、病気の治療や再発防止、合併症予防などを目指して栄養を管理します。主な実務は、患者への食事管理・献立作成・調理・栄養指導などです。医師や看護師と連携し、栄養の専門職として高度な知識や技術を活かします。
企業や行政
食品メーカーや研究機関では、食に関する研究や、機能性食品の開発、管理栄養士・栄養士の養成などを行います。主な業務は企画立案・研究開発・市場調査です。スポーツ関連施設では、栄養指導や食生活のアドバイスなどを行うこともあります。
飲食店やレストラン、社員食堂などでは、献立作成・メニュー考案・食材発注などを行っています。カロリー表示の計算も栄養士や管理栄養士の仕事です。
保健所や保険センター、市役所などでは、地域住民の健康づくりに栄養と食生活指導の面から働きかけるのが仕事です。母子から高齢者まで、幅広く栄養相談や栄養指導を行います。なお、自治体に配置される場合は地方公務員試験を受けて採用される必要があります。
栄養士養成施設での学び方
栄養士・管理栄養士養成施設では、それぞれの施設で学べることが違います。授業やカリキュラムは、人の栄養状態を分析して評価・判断する「栄養指導論」、調理器具の扱いや調理法を学ぶ「調理学実習」、給食管理に関して下処理から機械の洗浄まで衛生的な維持を実践で学ぶ「給食管理」などさまざまですが、すべての施設で同じことが学べるとは限りません。そのため、将来の働き方や目的に基づいて養成施設を選ぶと、より学びが深まるでしょう。
管理栄養士国家試験の準備と対策
管理栄養士国家試験は、試験までに実務経験のブランクが空いていても、条件を満たしていれば受験が可能です。
国家試験の準備をする際は、まずは年間スケジュールを把握し全体の見通しを立ててから学習計画を管理しましょう。過去問を中心に勉強すると、学習範囲・量ともに効率良く勉強ができます。模擬試験で実力をチェックしながら勉強すれば、覚えたいポイントや間違えやすいポイントも重点的にチェックできるでしょう。
栄養士・管理栄養士として仕事復帰を目指す場合は、基礎学習に時間を割くよりは、限られた時間を有効に活用し、過去問を中心に実践的にこなすことが合格への近道です。
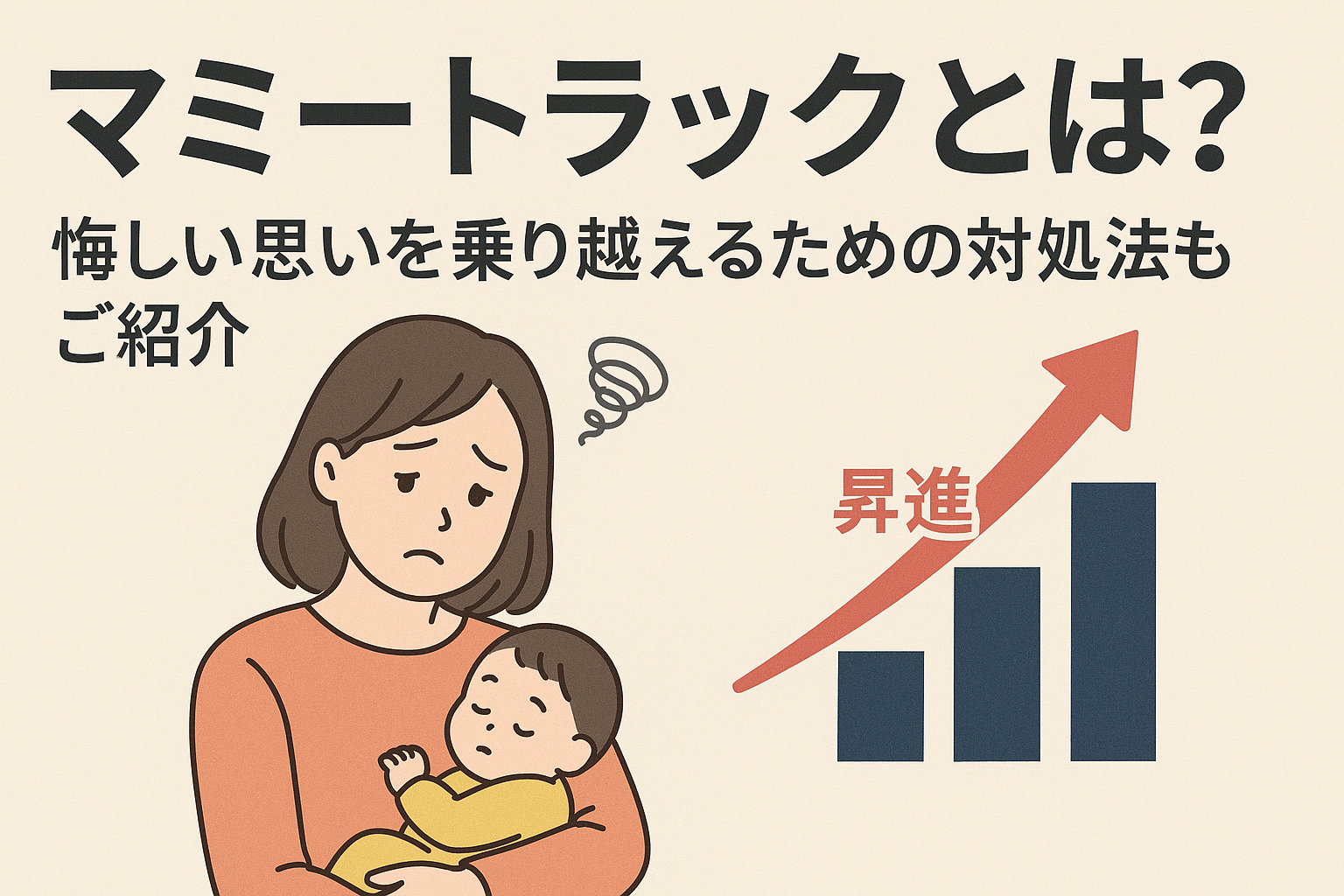
.png)