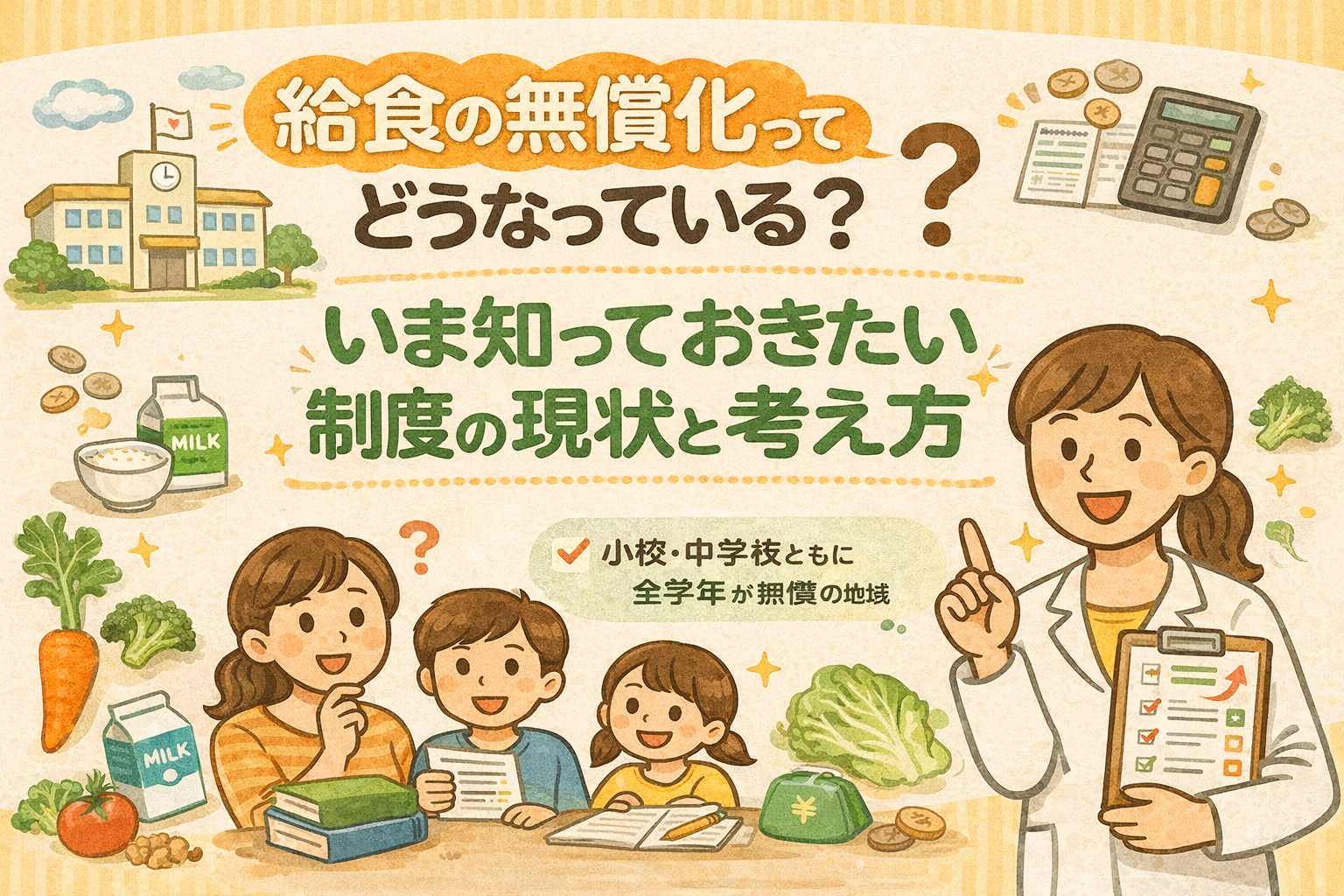赤ちゃんの成長に欠かせないものの一つが「乳児期の食事」です。
乳児期の食事をスタートすることは、母乳やミルクだけでは補えない栄養素を、食事を通じて少しずつ取り入れる大切なステップです。
しかし、「いつから何をあげればいいの?」「どれくらいの量が適切?」と不安や疑問を感じるママも多いでしょう。
そこでこの記事では、乳児期の食事の基本と進め方のポイントを、月齢別にわかりやすく解説します。
乳児期の食事についての基本の考え方
乳児期の食事の定義と目的
乳児期の食事は、母乳やミルクだけでは補いきれなくなる栄養素を、日常の食事から少しずつ取り入れていくためにあります。
赤ちゃんが食べ物を「飲み込む」から「噛んで飲み込む」へと移行する中で、食べる力や習慣を育てることが目的です。
この時期の食事は、単に栄養補給のためだけでなく、「食べることへの興味」を育み、「家族と食卓を囲む楽しさ」を知る、重要な体験でもあります。
また、将来の偏食を減らすためにも、初期の段階でさまざまな食材を経験させることが推奨されています。ただし、体の機能がまだ発達途中である乳児には、食材の選び方や調理の仕方に細心の注意が必要です。
乳児期の食事を始める時期の目安
乳児期の食事は一般的に、生後5~6ヵ月頃から始めるのが目安とされています。
この時期になると、赤ちゃんは以下のような変化を見せ始めます。
- 首がしっかりすわる
- 支えがあれば座れる
- 食べ物に興味を示す
- スプーンを口に入れても舌で押し出さない
こうしたサインが見られれば、離乳食を始める準備が整ってきたと考えられます。
ただし、発達スピードには個人差があるため、月齢にとらわれすぎず、赤ちゃんの様子をよく観察しながら始めることが大切です。
また、乳児期の食事は、あくまでも固形食に“慣れるため”のもの。無理に食べさせようとせず、笑顔で見守ることが、食事への良いイメージづけにつながります。食事の時間が赤ちゃんにとってもママにとっても「楽しい時間」になるよう、ゆとりを持ったスケジュールで進めましょう。
発達に合わせた乳児期の食事の進め方
離乳食は赤ちゃんの発達段階に合わせて、段階的に進めることが基本です。それぞれの時期には特徴があり、食材の形状や量、調理法などを変えることで、無理なく“食べる力”を育てていくことができます。
5~6ヵ月:ゴックン期
離乳食スタートの時期です。舌の動きが未熟なため、母乳やミルク以外の食べ物を「ごっくん」と飲み込む練習から始めます。
ゴックン期のポイントは、次の4点です。
- なめらかな10倍がゆからスタート
- 野菜はやわらかく茹でてすり潰す
- アレルギーのリスクを考え、一度に複数の新しい食材を食べさせることは避ける
- スプーンひとさじから様子を見て進める
この段階では特に「食べる」よりも「慣れる」ことが目的です。赤ちゃんの表情や反応を見ながら、リラックスして取り組みましょう。
7~8ヵ月:モグモグ期
生後7~8ヵ月は、舌でつぶす動きができるようになる時期で、食べ物の形状も少しずつ「粒のある状態」に移行していきます。取り入れられる栄養素も多様になり、たんぱく質源の食材も少しずつ食べさせられるようになります。
モグモグ期のポイントは、次の5点です。
- おかゆは7倍がゆに移行する
- 野菜はみじん切り~粗つぶし程度の大きさにする
- 豆腐、白身魚、ささみなども取り入れる
- 1日2回食にし、食事リズムを整える
この時期に「手づかみ食べ」を始める赤ちゃんもおり、五感を使った食体験が重要になります。
9~11ヵ月:カミカミ期
歯ぐきでつぶす力がついてくる9~11ヵ月では、食事の形状もさらにステップアップします。手づかみやスプーンを持ちたがる行動も見られるようになります。
カミカミ期のポイントは、次の4点です。
- おかゆは5倍がゆ~軟飯に
- 野菜・肉・魚は歯ぐきでつぶせる硬さ(バナナくらい)に
- 手づかみできるおかずを取り入れる
- 1日3回食へ移行し、食後に授乳する
家族と一緒の食卓を経験することで、食事の時間に楽しさが加わり、食べる意欲がさらに高まります。
12~18ヵ月:パクパク期
いわゆる「完了期」に入るこの時期は、大人と同じような食材を、味付けを薄めにして提供できるようになります。咀嚼の力もつき、自分で食べる意欲も旺盛になる頃です。
パクパク期のポイントは、次の4点です。
- 普通のごはん(軟飯)を目指す
- おかずも形がはっきりしたものに
- 調味料は極力使わず、素材の味を活かす
- 食事と授乳をはっきり分け、自立した食事へ移行していく
ただし、飲み込みや咀嚼が未熟な面もあるため、喉に詰まりやすい食材(こんにゃく、もち、ナッツなど)は避けましょう。
乳児期の食事でよくあるお悩み
食べてくれない、ムラがある
「せっかく作ったのに全然食べてくれない」「昨日は食べたのに、今日は一口も口にしない」など、食べムラは非常に多くの保護者が経験する悩みです。
これは、赤ちゃんにとって「食べる」ことがまだ学びの途中であり、日々の体調や気分、環境の変化にも大きく影響されるためです。
こうした場合には、無理に食べさせるのではなく、赤ちゃんのペースを尊重してあげることが大切です。
また、手づかみ食べや食器の工夫で食べる意欲を引き出すのも効果的です。
アレルギーが心配
もう一つの大きな不安は、「アレルギーが出たらどうしよう」という点です。特に初めて与える卵・小麦・乳製品といった食材は、慎重に進める必要があります。
初めての食材は「少量」「午前中」「1種類のみ」を基本とし、万が一の変化にすぐ気づけるようにしておくと安心です。
また、湿疹や嘔吐などの症状が出た場合には、すぐに医療機関を受診することが重要です。
乳児期の食事をスムーズに進めるためのポイント
月齢ごとの段階に沿って進める
それぞれの段階での目的を把握しながら進めることが大切です。ゴックン期では“飲み込みの練習”、パクパク期では“自分で食べる意欲”を育てることが主な目的となります。
食事のリズムを整える
「朝・昼・夕」の生活リズムを意識して食事を設定することで、赤ちゃんの胃腸の働きが整い、排便や睡眠のサイクルにも良い影響を与えるとされています。
無理をしない・頑張りすぎない
市販のベビーフードや冷凍ストックを活用し、手間を大幅に減らすことで、ママの負担を軽くしましょう。
五感で楽しめる乳児期の食事づくり
食材の色や香り、舌触りなど五感に訴える工夫をすることで、赤ちゃんの興味を引き出しやすくなります。
まとめ
乳児期の食事は、赤ちゃんの身体的・精神的な成長を支える大切なものです。ただ栄養を補うだけではなく、「食べる」という行為そのものに慣れ、楽しさを感じてもらうことが、この時期の食育において非常に重要です。